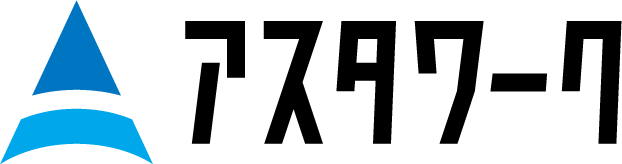無職になったらやるべきこと11個のこと 誰も教えてくれない タダでもらえるお金
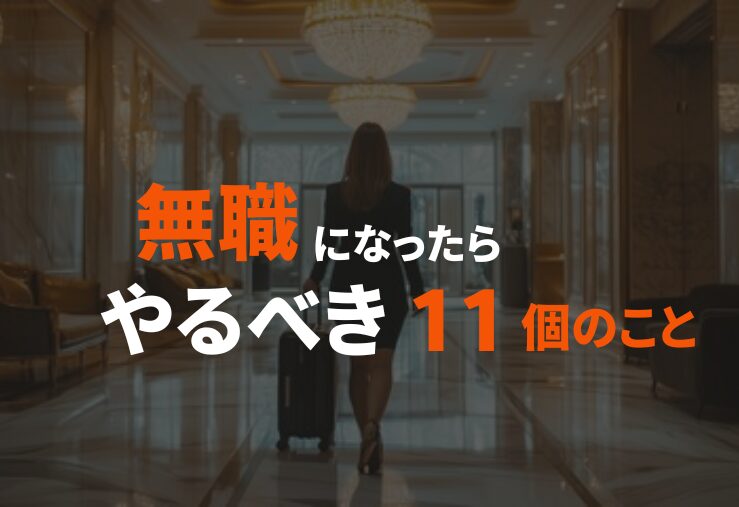
目次
無職になったらまず何からはじめるべきか?無職になったことで、多くの人ににって大きな転機となります。新たなキャリアを模索する機会としてとらえる一方で、生活基盤を維持するための手続きが必要です。特にハローワークや役場での手続きは、経済的安定を保つために非常に重要です。この記事では、無職になった際の必要な手続きについて詳しく解説します。
給付金・手当一覧表
|
制度・給付名 |
条件 |
窓口 |
申請期限 |
備考 |
|
失業保険 |
離職前2年間に12ヶ月以上雇用保険に加入していたなど |
ハローワーク |
退職後1年以内 |
金額や期間は、退職理由や年齢、加入年数によって異なる |
|
住宅確保給付金 |
住居喪失の恐れがあり、収入・資産が一定以下の場合 |
市区町村の自治る相談支援窓口 |
離職後2年以内(原則) |
家賃相当額が一定期間支給(上限あり) |
|
職業訓練受講給付金 |
雇用保険を受けられない人がハローワークの認定を受けて職業訓練を受講 |
ハローワーク |
訓練開始前までに申請(受講決定前) |
月額10万円+交通費支給(条件あり) |
|
教育訓練給付金(一般教育訓練給付金) |
雇用保険の被保険者期間が通算3年以上(初回のみ1年以上)あること |
ハローワーク |
受講開始の1ヶ月前までに申請(原則) |
厚生労働大臣が指定する講座を受講・修了した場合、支払った教育訓練費の20%(上限10万円)が支給される |
|
教育訓練給付金(専門実践教育訓練給付金) |
雇用保険の被保険者期間が通算3年以上(初回のみ2年以上)あること |
ハローワーク |
受講開始の1ヶ月前までに申請(原則) |
専門的・実践的な教育訓練を受講・修了した場合、支払った教育訓練費の50%(年間上限40万円、最大3年間)が支給される |
|
広域求職活動費 |
雇用保険の受講支給資格者であり、ハローワークの紹介で遠隔地の事業所を訪問する場合 |
ハローワーク |
活動前に申請(原則事前承認人が必要) |
ハローワークの紹介により、遠隔地(往復200km以上)の事業所での面接等を行う際、交通費や宿泊費が支給される |
|
退職給付金制度(退職一時金制度・確定給付企業年金制度DB・確定拠出年k人制度DC |
企業が独自に設ける退職金一時金や企業年金制度など、退職時に支給されるき給付金制度 |
勤務先の人事・総務部など |
就業規則・契約による |
これらの制度の有無や内容は企業によって異なる |
免除系一覧表
|
制度・給付名 |
条件 |
窓口 |
申請期限 |
備考 |
|
国民年金保険料の免除・猶予制度 |
失業により収入が減少 |
市区町村の年金窓口(または年金事務所) |
原則、対象年度の翌年6月末まで |
全額・一部免除、または納付猶予が可能 |
|
国民健康保険料の免除 |
退職・失業による収入減少 |
市区町村の国保担当課 |
自治体によって異なる |
退職による特例で前年の給与所得を30/100とみなして軽減されるケースあり |
|
住民税の免除・猶予 |
退職により収入が大きく減った場合 |
市区町村の税務課 |
納付通知後、支払期日前まで |
減免・分納・徴収猶予など相談可能 |
再就職が決まったらやるべき一覧表
|
制度・給付名 |
条件 |
窓口 |
申請期限 |
備考 |
|
再就職手当 |
失業保険の受給資格がある人が早期に再就職した場合 |
ハローワーク |
再就業後1ヶ月以内(または再就職後早めに) |
|
|
就業促進定着手当 |
再就職手当を受給し、再就職先で6ヶ月以上継続して雇用保険の被保険者として働いている事 |
ハローワーク |
再就職後6ヶ月経過から2ヶ月以内 |
再就職手当を受給した方が、再就職後6ヶ月間の給与が前職より低い場合、その差額の一部が支給sされる |
|
移転費 |
雇用保険の受給資格者であり、ハローワークの紹介で遠隔地への転居を伴う就職または訓練を行う場合 |
ハローワーク |
原則、移転前に申請(事前相談が必須) |
ハローワークの紹介により、遠隔地の事業所に就職または公共職業訓練を受講するために転居する場合、引っ越し費用や移転料が支給される |
無職になったらまず取り組むべき手続き

雇用保険(失業保険)の手続き

1.会社を退社する際に、離職票の発行を依頼
退職時に会社から「離職票」を受け取ります。この書類は失業保険を申請する際に必須です。離職票には退職理由が記載されており、受給条件に影響を与えるため、内容に誤りがないか確認してください。失業保険は、無職になった際の生活費を補助するための制度です。以下の手順で進めます。
2.ハローワークで申請
お住いの地域を管轄するハローワークで求職申し込みを行い、離職票を提出します。申請後、7日間の待機期間が設けられます。自己都合退職の場合は、さらに1ヶ月の給付制限期間があります。(2025年4月改正後)
3.初回説明会への参加
受給資格が確定すると、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を受け取ります。その後、指定された初回説明会に参加します。
4.失業認定と基本手当の受給
失業認定申告書に求職活動実績を記入し、ハローワークで失業認定を受けます。認定後、5営業日程度で基本手当が振りこまれます。以降は4週間ごとに認定を受ける必要があります。
【2025年4月改正】失業保険支給の概要
2025年4月から施行された雇用保険法のの改正により、自己都合退職者の失業保険給付制限期間が従来の2ヶ月から1ヶ月に短縮されました。この改正は、自己都合退職者がより早く失業給付を受けられるようにすることで、経済的な負担を軽減し、早期の再就職を支援することを目的としています。
【2025年3月までと4月以降】の失業保険 給付比較
|
項目 |
2025年3月までの制度 |
2025年4月改正後 |
|
給付制限期間 |
2ヶ月 |
1ヶ月(原則) |
|
教育訓練の高価 |
制限解除なし |
受講で制限解除可能 |
|
頻繁な離職者への対応 |
未特化 |
5年3回以上で3ヶ月制限 |
|
支給開始までの期間例 |
約2.5ヶ月 |
約1.5ヶ月 |
失業保険の主な変更点の解説
1.給付制限期間の短縮
自己都合退職の場合、失業保険の支給開始までにかかる期間が「待機期間7日+制限2ヶ月」から「待機7日+制限1ヶ月」に短縮されます。
2.教育訓練による制限解除
離職前1年以内または離職後、教育訓練給付対象の講座を受講した場合、給付制限が解除されます。これにより、待機期間終了後すぐに失業保険を受け取れるようになります。
3.頻繁な離職者への厳格化
過去5年間に3回以上自己都合退職を繰り返した場合、給付制限が3ヶ月に延長されます。この措置は安易な転職を抑制する目的で導入されています。」
【2025年4月改正後】の給付制限期間について具体例
1.待機期間(7日間)
まず、ハローワークで求職申し込みをした日から7日間は「待機期間」となります。この間は、全員一律で失業保険は支給されません。
2.給付制限期間(1ヶ月間)
自己都合退職の場合、待機期間が終わった後さらに1ヶ月間の「給付制限期間」があります。この1ヶ月間も失業保険は支給されません。
3.支給開始
待機期間(7日間)+給付制限期間(1ヶ月)が修了した翌日から、失業保険の支給が始まります。
例えば、
退職日:2025年4月1日に自己都合で退職
ハローワークで手続きした日:4月2日
|
日付 |
状況 |
|
2025年4月2日 |
ハローワークで手続き開始 |
|
2025年4月2日~4月8日 |
待機期間(7日間) |
|
2025年4月9日~5月8日 |
給付制限期間(1ヶ月) |
|
2025年5月9日以降 |
失業保険の支給開始 |
健康保険の変更手続き

退職すると会社の健康保険から脱退するため、新たな健康保険への加入手続きが必要です。
▶選択肢の全体像
健康保険は以下の3つの選択肢から選べます。
・国民健康保険への加入
・任意継続被保険者制度
・家族の扶養に入る
・国民健康保険への加入
市区町村役場で手続きを行います。(退職後14日以内に届け手が必要です)
・任意継続被保険者制度
退職前の健康保険を継続する制度です。(退職後20日以内に申請すれば、)最大2年間継続可能ですが、保険料は全額自己負担となります。
・家族の扶養に入る
配偶者などの被扶養者になる制度です。手続き期限は随時できます。
▶国民健康保険への切り替え
1.退職日の確認
会社が健康保険の資格喪失の手続きを行うため、退職日を性格に把握
2.必要書類の準備
・健康保険資格喪失証明書(会社発行)
・本人確認書類(運転免許証など)
・印鑑
・年金手帳(任意)
3.市区町村役場へ申請
退職日の翌日から14日以内に居住地の窓口で手続き
注意点
・保険料の遡って徴収:14日を過ぎても手続き可能ですが、退職日翌日から計算された保険料を全額支払う必要があります
・扶養制度なし:家族がいる場合、全員が個別に加入する必要があります
・2025年改正:保険料上限が年間3万円引き上げ(所得による)
▶任意継続被保険者制度
適用条件
・退職前の健康保険に2ヶ月以上継続加入
・退職後20日以内に申請
メリット・デメリット
|
項目 |
任意継続 |
国民健康保険 |
|
保険料 |
会社負担も自己負担(全額) |
所得に応じた金額 |
|
期間 |
最長2年間 |
無期限(加入中) |
|
扶養家族 |
継続可能 |
個別加入 |
|
手続き簡便性 |
元の保険証が継続使用 |
新規保険証の発行 |
▶家族の扶養に入る場合
条件
・年収130万円未満(60歳以上は180万円未満)
・同居が原則(別居でも生計同一なら可能)
・扶養者の健康保険組合が承認
2025年改正の影響
・国民健康保険料:上限額が年間3万円引き上げ
・任意継続:保険料計算が2025年4月改定料率適用(協会けんぽの場合)
・マイナ保険証:2025年12月以降は従来の保険証が使えなくなるため、手続き時にマイナンバーカードの提示が必要
任意継続と国民健康保険では、年収いくらまでがどっちが得とかある?
基本原則
|
年収帯 |
有利な制度 |
主な理由 |
|
~400万円 |
国民健康保険 |
所得比例の保険料計算が低所得者に有利 |
|
400~500万円 |
ケースバイケース |
扶養家族の有無や地域差が影響 |
|
500万円~ |
任意継続 |
保険料上限(約38万円/年)が効き、高所得者ほど有利 |
具体例(東京都23区・40歳未満・独身の場合)
|
年収 |
任意継続保険料(年) |
国民健康保険料(年) |
差額 |
|
300万 |
約31万2,000円 |
約24万8,000円 |
▲6.4万円 |
|
400万 |
約38万円1,000円 |
約33万3,000円 |
▲4.8万円 |
|
500万 |
約38万円1,000円 |
約42万5,000円 |
+4.4万円 |
|
700万 |
約38万1,000円 |
約61万4,000円 |
+23.3万円 |
※地域・家族構成で数値が変動するため注意
例外ケース
1.扶養家族がいる場合
・任意継続:家族分の保険料が追加されない
・国民健康保険:家族全員の平均割が加算
→年収400万円以下でも任意継続が有利な場合あり
2.地域差
・国民健康保険料は市区町村ごとに異なる
・例:大阪市では年収500万円でも国民健康保険が安い場合も
3.短期無職の場合
・任意継続は最長2年間の継続が可能
・再就職予定が早い場合は手続き簡便性を優先
年金の変更手続き

国民年金変更手続きの全体像
退職すると、厚生年金から国民年金(第1号被保険者)への切り替えが必要です。
国民年金保険変更の際の必須手続きの流れ
|
ステップ |
内容 |
期限 |
|
①退職日の確認 |
会社から「離職票」を受け取る |
退職日当日 |
|
②国民年金への切り替え |
市区町村役場で手続き |
退職後14日以内 |
|
③保険料の納付方法選択 |
口座振替/クレジット/納付書 |
手続き時 |
|
④免除制度の検討 |
所得に応じた減免申請 |
随時 |
・市区町村役場で手続き
国民年金への切り替えは退職後14日以内に行えます。配偶者が扶養内の場合も同様に届け出が必要です。
・免除や猶予制度の利用
経済的な理由で支払いが難しい場合は、免除や猶予制度を申請できます。
具体的な手続き内容
・必要書類(国民年金への切り替え)
✓年金手帳(基礎年金番号通知書)
✓離職票/退職証明書
✓本人確認書類(運転免許証など)
✓印鑑
✓通帳(口座振替希望の場合)
・手続き場所
住民票所在地の市区町村役場(国民年金担当窓口)
・注意点
・14日ルール:退職日の翌日から14日以内に手続き(例:4月1日退職→4月14日まで)
国民年金の免除・猶予制度の活用
|
制度名 |
対象者 |
特徴 |
|
全額免除 |
前年所得が基準以下 |
受給額50% |
|
一部免除 |
所得に応じ4段階 |
25%~75%減額 |
|
納付猶予 |
20~50歳未満 |
猶予期間も受給資格に参入 |
・申請方法:市区町村窓口で「免除・猶予申請書」を提出
・必要書類:雇用保険受給資格者証の写し/所得証明書
よくあるケース
ケース1:すぐに再就職する場合
・同一月中の転職:新会社が厚生年金手続き(自身の手続き不要)
(例)4月15日退職→4月20日入社→4月分は新会社が負担
・翌月以降の転職:空白期間分を国民年金でカバー
(例)4月30日退職→5月1日入社→4月分は自身で納付
ケース2:配偶者の扶養に入る場合
・条件:年収130万円未満(60歳以上は180万円未満)
・手続き:配偶者の会社に「被扶養者届」を提出→第3号被保険者に変更
住宅確保給付金

制度概要
住宅確保給付金は、失業や収入減少で家賃支払いが困難な人を対象に、最大9ヶ月間(最長12ヶ月)の家賃補助を行う制度です。
住宅確保給付金の受給条件
|
項目 |
内容 |
|
対象者 |
離職後2年以内or収入が離職時と同等以下に減少 |
|
収入基準 |
世帯月収が市区町村の基準額以下(例:単身世帯10万円、夫婦世帯15万円) |
|
資産要件 |
預貯金が単身50万円以下/夫婦75万円以下(※生活保護基準の2倍) |
|
居住実態 |
現在住居があるor新規契約予定 |
注意点
・2025年改正:マイナ保険証の提示が必須(従来の保険証は使用不可)
住宅確保給付金の支給額と期間
|
世帯類型 |
月額上限 |
支給期間 |
|
単身 |
53,700円 |
原則3ヶ月 |
|
2人世帯 |
64,000円 |
(最長9ヶ月) |
|
3人以上世帯 |
69,000円 |
※延長可能 |
住宅確保給付金の申請に必要な書類
1.本人確認書類
・運転免許証(両面)
・マイナンバーカード
・健康保険証+住民票の写し
2.収入証明
・直近3ヶ月の給与明細
・雇用保険受給資格者証の写し
・銀行通帳(全ページコピー)
3.居住関係書類
・賃貸契約書の写し
・入居予定証明書(新規契約の場合)
4.その他
・住居確保給付金申請時確認書(ハローワーク発行)
・自立相談支援事業の受付票
2025年改正のポイント
・電子申請拡充:一部自治体でオンライン申請可能に
・虚偽申請対策:マイナンバー連携による収入確認強化
・支援プラン厳格化:就職活動記録のデジタル管理導入
「雇用保険受給資格者証」「賃貸契約書」「直近3ヶ月の通帳コピー」を優先的に準備。特に収入基準は厳格にチェックされるため、アルバイト収入がある場合は事前に計算しておきましょう。支給中は自治体の支援プログラムに積極的に参加することが継続受給の鍵です。
職業訓練受講給付金制度

収入がない求職者が職業訓練を受けながら、月10万円+交通費をもらえる制度。
生活を支えながら再就職に役立つスキルを身につけられる制度です。
職業訓練受講給付金制度の対象者
以下のすべてに該当する方が対象
1.ハローワークに求職申し込みをしている人
2.雇用保険を受給できない(もしくは受給が終わった)人
3.本人の収入が月8万円以下(世帯全体での制限もあり)
4.訓練を受ける強い意思があり、支援計画に同意出来る人
5.世帯の中で同様の支援を受けている人がいないこと
職業訓練受講給付金制度で貰えるお金
|
内容 |
金額支援内容 |
|
①訓練期間中の給付金 |
月額10万円(非課税) |
|
②通所交通費 |
実費支給(上限あり) |
|
③(条件により)託児費用補助 |
託児支援も別途あり(自治体連携) |
職業訓練受講給付金制度で受けられる訓練
・Word、Exele、プログラミングなどのパソコン系
・医療事務、介護、簿記などの資格系
・IT、デザイン、製造、接客など他分野
※訓練はすべて無料(※テキスト代など一部自己負担あり)
※月~金の平日、9:00~16:00くらいのフルタイムが基本
職業訓練受講給付金制度の申請タイミング
・訓練開始前までに申請・審査が完了している必要があります
・訓練校の募集時期もあるため、余裕をもって1~2ヶ月前に相談しましょう
職業訓練受講給付金制度の申請に必要な書類
1.本人確認書類
・運転免許証/パスポート/在留カード
・マイナンバーカード(通知カード+身分証の併用も可)
2.申請用紙(ハローワーク交付)
・受講申込・事前審査書(安定所提出用)
・職業訓練受講給付金支給申請書
・職業訓練受講給付金通所届
3.収入・資産証明
・本人:直近3ヶ月の給与明細/源泉徴収票
・世帯:前年分の所得証明書(市区町村発行)
・失業中:雇用保険受給資格者証の写し
・本人/家族全員の預貯金通帳(直近1ヶ月分・全ページ)
・50万円以上残高がある講座の残高証明書
4.住民票
・3ヶ月以内発行の写し(世帯全員記載)
・マイナンバー記載ありの場合は身分証省略可能
5.受講証明
・訓練機関の合格通知書/受講申込書
・訓練内容が記載されたパンフレット(任意)
教育訓練給付金

雇用保険加入者がスキルアップのために受講する教育訓練費用の一部を国が補助する制度です。2025年4月時点で3種類の給付金が存在し、それぞれ対象講座と支給額が異なります。
3種類の給付金比較
|
種類 |
支給率 |
上限額 |
対象例 |
|
一般教育訓練 |
20% |
10万円 |
簿記・TOEIC・社会保険労務士 |
|
特定一般教育訓練 |
40% |
20万円 |
介護職員初任者研修・大型免許 |
|
専門実践教育訓練 |
50~80% |
年56万円 |
看護師・保育士・IT専門課程 |
※専門実績は資格取得後、就職かつ賃金5%以上上昇で70%→80%に支給率アップ
教育訓練給付金の受給条件
1.雇用保険加入歴
・初回利用:1年以上の加入(専門実践は2年以上)
・過去利用歴あり:前回受講から3年以上経過
2.受講タイミング
・在職中or離職後1年以内(最大4年まで延長可能な場合あり)
3.対象講座
・厚生労働大臣指定の教育訓練機関で受講
追加要件(専門実践)
・45歳未満で失業中の場合、月額10万円の「教育訓練支援給付金」併給可能
・修了後1年以内に就職し、賃金5%以上上昇で追加給付
教育訓練給付金の申請に必要な書類
・教育訓練給付金申請書
・教育訓練修了証明書
・領収書orクレジット証明書
・運転免許証/マイナンバーカード
・雇用保険被保険者証
2025年改正のポイント
・電子申請拡充:マイナポータル経由でオンライン申請可能に
・対象講座拡大:AI・DX関連講座が新規追加
・支給率改定:専門実践の上限が年56万円→64万円(2025年10月以降)
広域求職活動費

雇用保険受給者が遠方の求人に面接する際、交通費と宿泊費の一部を国が負担する制度です。居住地から片道100km以上離れた事業所への面接が対象で、最大42,500円/月の支援が受けられます。
広域求職活動費の支給条件
1.雇用保険受給資格
・失業保険の基本手当受給中
・待機期間(7日間)経過後
2.距離要件
・ハローワーク管轄区域間の往復距離200km以上(鉄道基準)
・例:東京→大阪(片道約550km)は対象
3.求人条件
・ハローワーク経由で紹介された常用求人
・事業所が交通費を全額負担していない
4.タイミング
・面接後10日以内に申請(2年以内であれば事項援用可能)
広域求職活動費の支給内容
|
費用種別 |
計算方法 |
上限額 |
|
交通費 |
最安・最短経路の実費 |
42,500円/月 |
|
宿泊費 |
1泊8,500円×必要日数 |
2泊まで |
|
航空機利用 |
エコノミークラス運賃(領収書必須) |
実費全額 |
広域求職活動費 申請に必要な書類
1.広域求職活動支持書(ハローワーク発行)
2.広域求職活動面接等訪問証明書(企業記入)
3.雇用保険受給資格証明書
4.支給申請書(ハローワーク様式)
5.航空機利用時:領収書原本
2025年改正のポイント
・電子申請拡充:マイナポータル経由でオンライン申請可能
・対象地域拡大:被災地域(東北・茨城)の求人で要件緩和
・支給上限改定:航空機利用時の上限撤廃(エコノミー全額対象)
住民税の免除・猶予制度

住民税には「所得割」と「均等割」があり、それぞれ免除基準が異なります。2025年現在、主に以下の3パターンで免除が適用されます。
住民税 全額免除の条件
▶自動免除
・生活保護受給者
・障害者・未成年者・寡婦/寡夫・ひとり親で前年所得135万円以下(給与所得:年収204.4万円未満)
▶所得基準免除
|
世帯累型 |
計算式(総所得金額) |
具体例(単身) |
|
単身世帯 |
45万円以下 |
給与収入100万円以下 |
|
扶養あり |
35万円×世帯人数+31万円以下 |
夫婦+子1人:141万円以下 |
住民税 部分免除(減額措置)
主に高齢者や低所得者向けの制度
|
減額割合 |
対象例 |
必要書類 |
|
7割 |
収入が低く生活困窮 |
収入証明・通帳写し |
|
5割 |
災害・疾病など特別事情 |
診断書・罹災証明 |
|
2割 |
収入減少が一時的 |
雇用保険受給資格証 |
住民税 猶予制度の詳細
申請条件
・失業・事業廃止・災害等による収入激減
・資産(現預金)が生活費3ヶ月分以下
猶予機関
・通常猶予:1年単位(最長3年)
・特別猶予:災害時は5年まで延長可能
必要書類
1.住民税猶予申請書(市区町村様式)
2.収入源を証明する書類(給与明細/納税通知書)
3.資産状況報告書(預金通帳全貢コピー)
再就職手当
失業保険受給者が早期に再就職した際、支給残日数に応じた一時金を受け取れる制度です。2025年4月改正により、給付内容が一部変更されます。
主な給付金の種類
|
給付金 |
支給条件 |
支給額(2025年4月以降) |
|
再就職手当 |
1年以上の雇用見込みがある職に就職 |
支給残日数の60~70% |
|
就業促進定着手当 |
離職前より賃金が低下し6ヶ月継続 |
支給残日数の20% |
|
就業手当 |
1年未満の短期雇用で就職 |
基本手当日額の30% |
※就業手当は2025年4月廃止
再就職手当の受給条件
1.雇用保険受給資格
・失業保険の支給残日数が1/3以上(45日以上)
・失業認定日から再就職までに空白機期間なし
2.雇用形態
・1年以上の雇用見込みがある常用職
・使用期間を含む(条件月採用も対象)
3.手続き期間
・再就職後1ヶ月以内に申請(時効:2年)
4.除外条件
・自営業・役員就任
・前職と同じ業種(例外あり)
支給額の計算方法
支給額=基本手当日額×支給残日数×係数(0.6or0.7)
係数決定基準
・0.7:支給残日数が所定給付日数の2/3以上
・0.6:支給残日数が所定給付日数の⅓~⅔
再就職手当申請に必要な書類
1.採用証明書(再就職先作成)
2.再就職手当支給申請書(ハローワーク様式)
3.雇用保険受給資格者証
4.失業認定申告書
5.勤務実績証明書(過去の就業記録)
※2025年4月からマイナンバーカード提示必須
2025年改正のポイント
・就業手当廃止:短期雇用への支援打ち切り
・定着手当減額:支給上限が30%→20%に引き下げ
・デジタル申請義務化:マイナンバーカードによるオンライン申請推奨
就業促進定着手当

再就職手当受給者が前職より賃金が低下した場合、その差額を補填するための支援制度です。2025年4月改定で支給上限がお幅に引き下げられ、新制度が適用されます。
就業促進定着手当の受給条件
1.再就職手当の受給歴
・基本手当の支給残に数1/3以上(45日以上)で再就職手当を受給済み
2.継続雇用
・再就職先で6ヶ月以上雇用継続
・雇用保険被保険者としての加入(週20時間以上勤務)
3.賃金低下の証明
・再就職後6ヶ月間の1日あたり賃金が前職を下回る
支給額の計算
2025年4月改正後
支給額=基本手当日額×支給残日数×20%
改正前との比較
|
項目 |
2024年まで |
2025年4月以降 |
|
支給率 |
30~40% |
一律20% |
|
上限日数 |
残日数全額 |
残日数全額 |
|
併給制限 |
再就職手当と合算100% |
上限撤廃 |
移転費

雇用保険受給者が遠方への就職・就業訓練のために引っ越しが必要な場合、6種類の費用を国が補助する制度です。
支給対象費用
|
費用種別 |
補助内容 |
支給条件 |
|
鉄道賃 |
最安・最短経路の運賃 |
公共交通機関利用時 |
|
船賃 |
航路利用時の運賃 |
離島などで利用の場合 |
|
航空賃 |
エコノミークラス運賃 |
陸路異動が困難な場合 |
|
車賃 |
ガソリン代・高速料金 |
車移動が合理的な場合 |
|
移転料 |
引っ越し業者費用 |
距離に応じた定額支給 |
|
着後手当 |
新居での雑費補助 |
引っ越し後の生活初期費用 |
受給条件
1.雇用保険資格
・失業保険受給中or受給資格保有
・ハローワークの紹介による就職/訓練
2.距離要件
・就職先:往復200km以上(鉄道基準)
・訓練先:片道100km以上
3.引っ越し時期
・就職/訓練開始前後の1ヶ月以内
4.家族同伴
・生計を共にする家族の費用も対象
申請に必要な書類
1.移動費支給申請書(ハローワーク様式)
2.雇用保険受給資格者証
3.引っ越し費用の領収証(交通費・業者費用)
4.家族同伴証明書(住民票・収入依存証明)
2025年改正のポイント
・電子申請拡充:マイナポータル経由でオンライン申請可能
・航空費緩和:LCC利用可能(事前承認必要)
・家族定義変更:事実婚パートナーを対象に追加
PROFILE:木村瞳。1985年生まれ。岡山県出身。大学卒業後ユニクロに入社し、採用や育成を担当。現職のアスタリスクへ2014年入社。面接や育成は通算15年以上携わっています。アスタリスクに入社してからは数多くの企業様へ訪問し人材コンサルの支援をさせて頂いています。その経験を活かし、現在は管理職として、幅広い職種の方の転職をサポートしています。
MESSAGE:取引先にも求職者の方にも忖度しないこと。良い情報も悪い情報も、お話しし、その方にとって間違いのない選択。リスクの低い選択をご提案できるように心がけています。
関連記事

あなたの『これから』を、今日から支える。15周年anniversary 特別プロジェクト~入社前応援・日給サポート開始~
15周年の感謝を、未来の従業員様へ。 おかげさまで、当社は…

ありがとう15周年!”働く理由”をもっと面白くー100万円キャンペーン
今、アスタリスクで働いている方も、これから働く新しい職場を探…
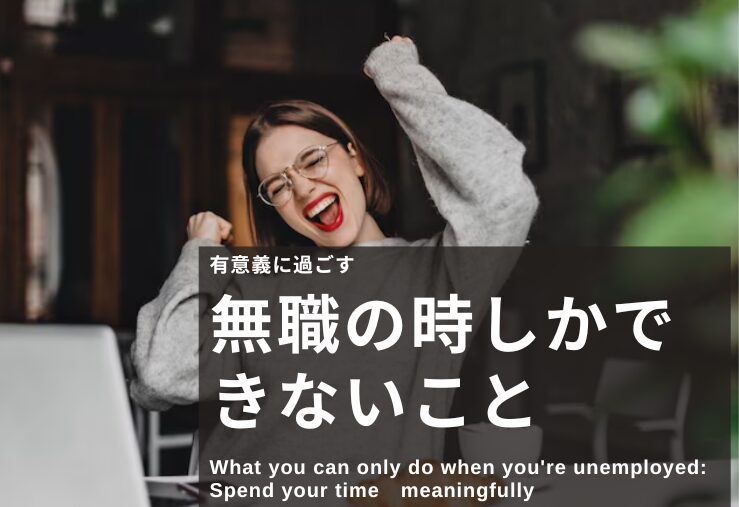
無職の時しかできないこと 過ごし方を工夫して有意義に過ごす
無職という期間は、様々なことに挑戦できる貴重な時間です。 …

大手企業と中小企業の比較。どちらがあなたに向いているのか?両方経験した30代の見解
大手企業と中小企業には、それぞれ独自の特徴や文化があります。…

ISFP(冒険家)の特性を活かせる、むいているお仕事
色々な仕事があって、選べる現代、自分にあった仕事が何か分から…

ISTP(巨匠タイプ)の特性を活かせる、むいているお仕事
色々な仕事があって、選べる現代、自分にあった仕事が何か分から…

ISTJ必見!特性を活かした向いている仕事を解説!
ISTJタイプの特性を最大限に活かし、安定した収入を得られる…

ISFJタイプ必見!自分らしく働ける職場の選び方
ISFJは「擁護者」とも呼ばれ、他人への思いやりや責任感が強…

ENFJの強みを120%発揮!あなたに合った仕事の見つけ方
自分に合った仕事をみつけることです。ENFJの強みを最大限に…
検索条件を1つ以上選択して下さい。
キーワードを入力して下さい。
自分にぴったりな求人を探す
キーワードから求人を探す